(外見上の特徴は、熱湯を浴びてただれたような感じです)
ができますので見た目で判断できます。
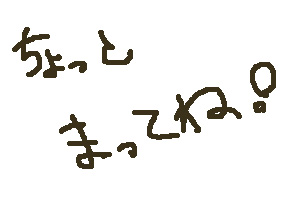
この病原菌は、腐敗し落下した果実の中で病巣の上に菌の核を形成し、そこで越冬します。
春になるとこの越冬菌が、第一次感染源になって病気を広めます。
そして第一次感染した実や葉などから、再び病原菌が飛散して第二次以降の感染を繰り
返し、広い範囲に蔓延していきます。
早期発見、早期駆除が基本になります。そのためには、病気にかかった実はもちろん、
枯れた枝は早めにせん定して取りのぞき、不要な徒長枝も切って通風をよくします。
ダコニールやトップジンMなどをで 春と秋を中心にした降雨の時期に、7〜10日間の間隔
で葉や実の部分に重点的に散布します。



