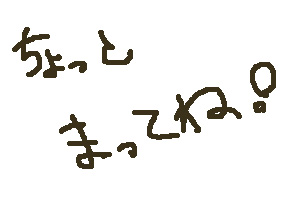病気になった部分の表面は、まるで灰白色の張り薬(膏薬 コウヤク)を貼ったように一面にカビが発生します。
この部分は、古くなると灰褐色に変色し、亀裂を生じてはげ落ちます。

カイガラムシの分泌物を栄養にして繁殖します。
この病気がひとたびはじまりますと、病原菌による被害とカイガラムシによる木の栄養分の吸収という、二重の被害を被ることになり
木はかなりのダメージを受けることになります。
そのためには 1月から2月に、石灰硫黄含剤や機械油乳剤を月に2〜3回 散布します。
またカイガラムシの発生時期である5月からはスミチオンやオルトラン、スプラサイド等を
月に2〜3回 枝や幹を中心に散布して駆除します。
カイガラムシを完全に駆除できるとコウヤク病の被害も沈静化の方向へ向かいます。